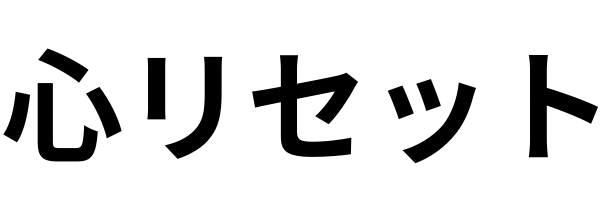共働きなのに、夫が家事をまったくしない…。
疲れて帰ってきても、気づけば自分だけが動いていて、
「なんで私ばかり?」と心が重くなる瞬間はありませんか?
夫婦で働いているはずなのに、家の中では“ワンオペ”のようになってしまう。
そんな負担の偏りは、あなたの努力不足でも、わがままでもありません。
実は“夫が家事をしない”背景には、
性格ややる気だけではない 見えにくい理由や構造的な問題 が隠れています。
この記事では、夫が家事をしない原因と、今日からできる現実的な対処法、
そして“私ばかり”にならないための家事分担の整え方を
やさしく、わかりやすくまとめています。
あなたの毎日がこれ以上しんどくならないように、
できるところから一緒に整えていきましょう。
夫が家事をしない“本当の理由”とは?

夫が家事をしない理由は、
「やる気がない」「ズボラ」「性格の問題」
そんな単純な話ではありません。
共働き家庭では特に、
家事の“見え方の違い”や、育ってきた価値観、役割分担の認識のズレ が大きく影響します。
妻側は“必要なタスク”が自然と目に入る一方で、
夫側は“家事の全体像”がそもそも見えていないことも多いのです。
さらに、家庭によっては
「母親が全部やっていた家庭環境」や
「家事は女性がやるもの」という価値観が無意識に残っていることも。
ここでは、
夫が家事をしない“本当の理由”を構造的に整理 し、
まずは問題の“土台”を明確にしていきます。
家事の“見える/見えない”差が大きい
共働きなのに家事の分担が偏ってしまう理由のひとつが、
家事に対する“見え方の差” です。
妻側
・やるべきことが自然と目に入る
・次に必要なタスクが直感的にわかる
夫側
・“家事の全体像”がそもそも見えていない
・どの作業をどの順番でやればいいか分からない
・タスク同士がどうつながっているのかが理解しにくい
⇒結果として夫は 「何もしない人」に見えてしまう んです。
でもこれは、
「やる気がないから」でも
「あなた任せにしているから」でもなく、
ただ単に 家事の“脳内マップ”が育っていない だけということも。
あなたが洗濯しながら夕飯の段取りを考えて動けるのは、
毎日の積み重ねで“家事の流れ”が体に染み込んでいるから。
夫はその経験値が不足しているせいで、
あなたのように家事全体を立体的に把握できていないのです。
もちろん、
そのズレが妻側のストレスになっているのも事実。
まずはこの“見え方の違い”を知るだけでも、
「どうして私ばっかり…」というつらさが
少し別の角度から見られるようになります。
育った環境や価値観の違い
夫が家事をしない理由の中で、
じつは大きなウエイトを占めるのが “育った家庭環境” です。
夫がこれまで実家で過ごしてきた環境が、
・実家で母親がすべて家事をしていた
・父親が家事に関わらないのが当たり前だった
・食事の準備から片付けまで「誰かがやってくれる」環境で育った
こんな背景のある男性は、
結婚後も無意識にその“家庭の形”をなぞろうとしてしまいます。
本人は悪気ゼロ。
むしろ“自分の中の普通”をそのまま出しているだけ。
だから妻側が
「なんで気づかないの?」
「なんで動かないの?」
と思ってしまう場面でも、
夫側は “気づくためのセンサー”がそもそも育っていない だけだったりします。
また、
「家事=女性がするもの」
という価値観が薄く残っているケースも多く、
・手伝ってあげているつもり
・家事は妻のほうが得意だから任せた方がいい
・自分は仕事で疲れているから妻がやるべき
という“古い思い込み”が、
無意識のうちに行動に影響していることもあります。
これらの価値観や習慣は、今日明日で変わるものではありません。
だけど、理解することで
「夫が家事しない=人格の問題」
と決めつけずに、仕組みや関係を整える方向に考えやすくなります。
 心リセット
心リセット僕自身も、実家では母親がほとんどの家事を担っていて、
「家事は誰かがやってくれるもの」という空気の中で育ちました。
結婚して初めて、その価値観のままだと妻に負担が偏ってしまうと実感。
育った環境の違いを知ることは、夫婦関係を整える第一歩なんだと感じています。
お願いしないと動けない“受動的家事”になっている
夫の家事スタイルが
「言われたらやる」
「頼まれた分だけやる」
という “受動的家事” になっているケースも非常に多いです。
これは、
自分で家事を“探して動く”経験が少ないことが原因です。
・何をやればいいかわからない
・どのタイミングで動けばいいかわからない
・そもそもタスクの存在に気づいていない
・「指示されたらやる仕事」だと思っている
こうした状態だと、
妻側が気を利かせて動くたびに、
夫はますます“受動型”に寄っていきます。
その結果、
妻は心身ともに疲れ切り、
夫は「俺は頼まれればやってるのに」と思い、
ふたりの認識が大きくズレてしまう。
大切なのは、
夫を“責める”ことではなく、
この受動スタイルが生まれる背景に
経験不足と役割の曖昧さ があると理解すること。
夫が家事をしない背景には、
“見え方の違い”“育った環境”“受動的家事”など、
さまざまな要因が重なっています。
だからこそ、
あなたひとりが全部背負わなければいけない理由は、どこにもありません。
次の章では、共働き家庭特有の“私ばかり”が生まれやすい仕組みを、
もう少し具体的に整理していきます。
夫へのイライラが積み重なってしんどいときは、こちらの記事も参考になります。
夫が家事をしない背景である、“見え方の差や価値観”などを詳しく解説しながら、その対処法まで紹介した内容となっています。

“私ばかり”になりやすい共働き家庭の落とし穴
共働きなのに家事の負担が“私ばかり”に偏ってしまう…。
これはあなたの努力不足ではなく、
共働き家庭に特有の“仕組みの問題” が大きく関係しています。
家庭の中には、気づきにくいけれど確かに存在する
「動きやすい側」と「動きにくい側」の差があります。
その差が放置されると、
いつの間にか片方だけが家事を背負ってしまいやすくなるのです。
ここでは、
なぜ妻側の負担が偏りがちなのかを 構造的に整理 していきます。
妻側が“動きやすい”構造になっている
共働きでも、家庭の中では
妻側が“動きやすい立場”に置かれやすい 傾向があります。
たとえば妻側は、
・仕事から帰ってすぐ“家モード”に切り替わる
・どこに何があるか把握している
・動かないと家が回らない不安がある
・家事が自然に目に入るクセがある
こうした要素が積み重なると、
自分では意識していなくても
“先に動いてしまう”状態になります。
一方で夫側は、
・生活動線の把握が浅い
・家事導線の経験が少ない
・必要なタスクに気づきにくい
という理由から、
「先に動く」のが純粋に難しい という状況になっています。
これが、
“動きやすい妻”と“受け身の夫”の構造をつくり、
結果として“私ばかり頑張っている”状態が生まれやすくなります。
家事が細分化されすぎて負担が見えにくい
家事は「1つの作業」に見えて、実は膨大な工程があります。
たとえば料理だけでも、
・献立を考える
・冷蔵庫を確認する
・買い物に行く
・食材を切る
・調理する
・片付ける
と、6〜7個に細分化されます。
でも夫側はこれを “料理という1タスク” と認識しがち。
つまり
妻:6〜7個のタスクとして認識
夫:1個として認識
この“タスク量の認知差”が
負担の不平等さを作り出します。
また、細かい家事が多いと
妻側ばかりが“気づきやすいタスク”を拾い続けてしまい、
結果として
見えない家事がすべて妻に積み重なる
という状態に。
これでは、疲れやすいのも当然です。
“気づいたほうがやる”が妻だけのルールになっている
共働き家庭の多くで根付いてしまうのが、
“気づいたほうがやる”ルール。
本来なら
気づいた人 → その人が動く
でいいはずです。
でも現実は…
・妻だけが気づく
・妻だけが動く
・夫は気づかないから動かない
・妻は動かないと家が回らない
という“片側ルール”になりがちです。
さらにこの状態が続くと、
- 妻:やらないと回らないから動く
- 夫:妻がやってくれるから気づかない
という 負のループ が強化されてしまいます。
これは、あなたが悪いわけでも、
夫が悪いわけでもなく、
単に
“気づきの差”が家事の差に直結してしまう構造
があるだけなんです。
こうした“構造的な落とし穴”が重なることで、
共働きでも家事の負担が妻側に偏ってしまいます。
でも、ここからできる対策は必ずあります。
次の章では、今日からできる 現実的な対処法 をまとめていきます。
共働きで“私ばかり家事してる…”と感じる背景は、家事そのものだけでなく、負担の偏りにも原因があります。
このテーマは別の記事で詳しくまとめています。

今日からできる、夫が家事しないときの対処法

「なんで私ばかり動いてるの…?」と思ったとき、
いきなり“完璧な家事分担”を目指す必要はありません。
まずは、
今日からできる小さな一歩 を整えることが大切です。
家事を丸ごと変えようとすると、妻側がさらに疲れてしまうため、
“負担を減らすための行動”を少しずつ積み重ねるのが効果的。
ここでは、
夫が家事をしないときでも あなたが自分をすり減らさずに済む方法 をまとめました。
まずは“あなたの負担”を減らすために距離を置く
夫が家事しない状況が続いていると、
あなたの心はずっと張りつめたままになっています。
そんな時にいきなり話し合おうとすると、
感情が爆発したり、余計に疲れてしまうことも。
だから最初にやるべきは、
家事と気持ちの距離を少しだけ置くこと。
・「今日だけ洗濯は明日に回そう」
・「夕食は簡単なものでOKにしよう」
・「帰宅後の10分は絶対に休む時間にする」
こうした“ちょっと手を抜く調整”で、
あなたの心にスペースが生まれます。
心が落ち着くだけで、
夫との向き合い方にも余裕が出てきます。
“何をしてほしいか”を短く・具体的に伝える
夫側は
「何をどうしてほしいか」が具体的に分からない
というケースがとても多いです。
なので、
お願いするときは長く説明しすぎず、
短く・具体的に・1つだけ 伝えるのが効果的。
・「洗濯物を“干すところまで”お願いしたい」
・「今夜の食器洗いを担当してほしい」
・「子どもをお風呂に入れてほしい」
“どう動けばいいかが明確”になるほど、
夫は動きやすくなります。
説明不足で伝わらないNG例
夫「何すればいいの?」
妻「え?いろいろあるでしょ?」
短く具体的なOK例
妻「今夜の食器洗いをお願いしたい。」
夫「了解!それならできるよ。」
そして、
「やってくれたことに軽く感謝を伝える」 ことで
夫の成功体験になり、次から自発的に動きやすくなります
家事のハードルを下げて“できる担当”を増やす
夫が家事をしない背景のひとつに、
“できる自信がない” というものがあります。
だから、
まずはハードルを少し下げて
夫が“できる担当”を増やすほうが効果的。
たとえば、
・「ゴミ出しだけ」→「ゴミ集め〜まとめて捨てる」までに広げる
・「お風呂掃除だけ」→「浴室全体の乾燥まで」
・「食器洗い」→「キッチン拭きまでセット」
最初は小さく、少しずつ幅を広げるイメージです。
こうすることで、
夫が“自分の役割”として家事を理解し、
受動的ではなく 自発的に動く土台 ができていきます。
今日できる小さな対処だけでも、
あなたの心の負担は大きく変わります。
ただ、根本的にラクになるには、
“家事の仕組み”そのものを整えていくことが必要です。
次の章では、夫婦で家事分担を続けやすくするための
長期的な改善のコツ をまとめていきます。
長期的に家事分担を整える“仕組みづくり”のコツ
夫が家事をしない状況を根本から変えるには、
その場しのぎのお願いや注意ではなく、
“仕組みそのもの”を整えることが欠かせません。
家事は毎日続くものだからこそ、
夫婦どちらかに負荷が偏ると、
小さなストレスが積み重なっていきます。
ここでは、
少しずつでも「続けやすい家事分担」に変えていくための
長期的な改善のコツ をお伝えします。
役割分担は“話し合い”ではなく“見える化”から始める
家事分担を決めようとすると、
つい“話し合い”から入ってしまいがちですが、
最初にやるべきなのは 見える化 です。
理由はシンプルで、
家事を細かく書き出すだけで、
夫はじめ「家事の全体像」が初めて共有されるから。
たとえば、
①食事の準備
②洗濯(干す・取り込む・畳む)
③掃除機かけ
④子供の送り迎え
⑤ゴミの管理
⑥買い出し
⑦名もなき家事(補充、整頓、片付け)
紙やスマホメモにリスト化するだけで、
「えっ、こんなにあるの?」
と夫が驚くことも珍しくありません。
ここで初めて、
ふたりが“同じ地図”の上に立てる。
この“地図づくり”が、家事分担のスタートラインです。
“お願いベース”ではなく“固定担当”をつくる
お願いベースだと、妻側の負担が減らないどころか、
「お願いするタスク」が増えてしまう ことも。
長期的にラクになるのは、
固定担当(レギュラー家事)をつくる方法。
夫
・洗濯
・お風呂掃除
・ゴミ出し
妻
・料理
・子供の寝かしつけ
“やる人が決まっている”というだけで、
妻が毎回「これお願いしてもいい?」と言う必要がなくなる。
固定担当は
“押し付け”ではなく、
夫が“自分の家事を把握できる仕組み”です。
負担の偏りがある場合は、
まずは夫に向いている作業から始めてOK。
少しずつ担当領域を増やしていけば、
夫の家事経験値が自然と育っていきます。
家事そのものを“減らす”選択肢を取り入れる
家事は分担しても、
根本の量が多ければしんどいまま。
だからこそ、
“家事を減らす”方向の調整も大事な仕組みづくり。
たとえば、
・週に2回は簡単な夕食(冷凍・ミールキット OK)
・掃除はロボットに任せる
・乾燥機付き洗濯機で時短
・買い物はネットスーパーに切り替える
・キッチンの数を減らす(調味料や道具をスリム化)
夫が動きやすくなる以前に、
家事そのものを軽くするだけで負担は大幅に軽くなる。
“頑張る量を減らす”という選択肢は、
立派な家事改善です。
夫婦の“当たり前”を一度ゼロにして見直す
家事の価値観は、育った家庭によって大きく違います。
その“違い”がすれ違いやイライラの原因になることも。
だからこそ、
「うちの家事の当たり前って、本当にこれでいい?」
と一度ゼロから見直す時間が必要です。
・母親が全部やっていた家庭で育った夫
・共働きが当たり前だった家庭で育った妻
・家事の優先順位がそもそも違う夫婦
・子育て中で“何を優先するか”がズレやすい2人
この見直しは、誰が悪いという話ではなく、
“違いをすり合わせる作業”。
ここを整えるだけで、
ふたりの家事ストレスがぐっと減ります。
仕組みを整えていくと、
家事が「誰かの善意」ではなく「ふたりの共同作業」に変わります。
少しずつでも改善すれば、必ずあなたの負担は軽くなります。
次の章では、
それでも苦しくなったときに役立つ
心の守り方 をまとめていきます。
“私ばかり頑張ってる…”と感じたときの心の守り方

共働きなのに、家事は自分ばかり。
夫は気づかず、私だけが疲れている…。
こんな状態が続くと、
どれだけ心が強い人でも限界を感じてしまいます。
でもこの「私ばかり…」という感覚は、
あなたがわがままだから生まれるのでも、
気にしすぎだから感じるものでもありません。
これは、毎日ちゃんと頑張ってきたあなたの心が、
「もう少し休ませて」と静かに訴えているサイン。
ここでは、そんな心を守るために
今日からできる小さなケアをまとめていきます。
そのしんどさは“あなたの弱さ”ではなく、努力の積み重ねの証
「私ばかり頑張ってる気がする…」
この気持ちは、心が弱っているから生まれるわけではありません。
むしろ、
毎日きちんと家を回し続けてきたからこそ
しんどくなるのです。
・朝から晩まで動き続けている
・気づいたタスクを拾い続けている
・家族の生活が乱れないように整えてきた
・仕事と家事の切り替えを何度も繰り返している
こうした負担を抱えながら頑張る毎日は、
誰が見ても“十分以上に頑張っている”状態です。
あなたが疲れているのは当然。
それほど、あなたが本気で日々を支えてきた証です。
“できない日”を自分に許す
共働きで家事も担っていると、
「今日は何もしたくない…」
という日が必ずあります。
そんな日は、
“できない自分”を責めるのではなく、許す日 にしてOK。
・洗濯は明日でいい
・ご飯は簡単なものにする
・部屋が多少ちらかっても気にしない
・子どもと一緒にゆっくりする時間を優先する
家事は毎日続くものだからこそ、
“休む日”をつくることは立派な“家事戦略”です。
自分を休ませることが、
長期的には家族のためにもなります。
一人になれる“自分の時間”を確保する
家事と仕事に追われていると、
自分の時間はあっという間に消えていきます。
だからこそ、
家事よりも“あなたの時間”を最優先する日 をつくることが大切です。
・ひとりで散歩する
・コンビニで好きなスイーツを買う
・ドラマを30分だけ見る
・カフェでゆっくりお茶をする
こうした小さな時間でも、
心がふっと軽くなり、
「また頑張ろう」と自然に思える力が戻ってきます。
これはサボりではありません。
心を保つための大切なメンテナンス。
「私ばかり頑張ってる」という気持ちは、
あなたの心が限界に近づいている合図です。
自分を責める必要はまったくありません。
このあと最後に、
この記事全体をふり返りながら、
家事の偏りは“あなたのせいじゃない”ということ を
改めてお伝えします。
まとめ:家事の偏りは“あなたのせい”じゃない。できることから整えていこう
共働きなのに、自分ばかり家事をしている…。
そんな毎日が続けば、誰だって疲れてしまいます。
でも、そのしんどさは あなたの努力不足ではありません。
夫が家事をしない背景には、
“見え方の違い”や“育った環境”、
“受動的家事”など、いくつもの理由が重なっています。
そこに、共働き家庭ならではの
「私ばかり動く」構造が重なることで、
あなたの負担はいつのまにか大きくなっていくのです。
今日からできる小さな対処として、
家事のハードルを下げたり、
具体的にお願いしたり、
自分の時間を優先するだけでも、
あなたの心は少しずつ軽くなります。
そして長期的には、
“見える化”や“固定担当”などの
家事の仕組みづくり が、
あなたの未来の負担を確実に減らしてくれます。
大切なのは、
あなたが限界を迎える前に、自分のしんどさを最優先にしてあげること。
家事はふたりで回すもの。
あなたひとりが背負う必要はどこにもありません。
どうかこれからは、
“頑張りすぎない家事”と
“あなたの心の余白”を大切にしていってくださいね。
あなたはもう、十分すぎるほど頑張っています。
もし今の気持ちに近いものがあれば、こちらも読んでみてください。
夫にイライラしてしまう…限界になる前に知ってほしい原因と対処法
共働きなのに夫にストレスを感じる理由と、限界になる前の対処法