会社の飲み会、周りに気を使いすぎてぐったり……。
でも、毎回断るのも気まずいし、できればうまく乗り切りたい。
そんなふうに感じている人は多いのではないでしょうか?
私も正直、いまだに飲み会が苦手です。
若いころは「そのうち慣れるだろう」と思っていたけれど、35歳になった今でも、やっぱり人付き合いの場は疲れてしまいます。
この経験から気づいたのは、「飲み会が苦手」は、経験の差ではなく“資質”の問題なんだということ。
無理して人に合わせようとするほど、どっと疲れてしまう。
それでも社会人として飲み会を完全に避けるのは難しいのが現実ですよね。
この記事では、そんな私の経験も交えながら、
「飲み会に参加しても気疲れしない考え方と行動」についてお話しします。
少し視点を変えるだけで、あの重たい気分をぐっと軽くできますよ。
なぜ飲み会はこんなに疲れるのか

うまく振る舞わなきゃと思うプレッシャー
職場の飲み会って、ただの「おしゃべりの場」ではなくて、どこか“仕事の延長”のような雰囲気がありますよね。
上司の前では気を抜けないし、後輩の前では先輩らしく振る舞わなきゃいけない。
「ちゃんと盛り上げないと」「気の利いたことを言わないと」と、自然体でいられない時間が続きます。
「自分だけ浮いてるかも」と思うと、無理に笑ったり話題を探したりして、終わるころにはぐったり…。
でもこれは“人付き合いが苦手”とかではなく、
周囲に合わせようとする「気遣いの多さ」が疲れの原因になっているんです。
過去の私は、うまく会話ができないのはお酒を飲む量が足りていないのだと、序盤にひたすら流し込んでしまい、後半に気分が悪くなってしまう…といった失敗を繰り返していました。
 心リセット
心リセットやっぱりビールはおいしいですね~
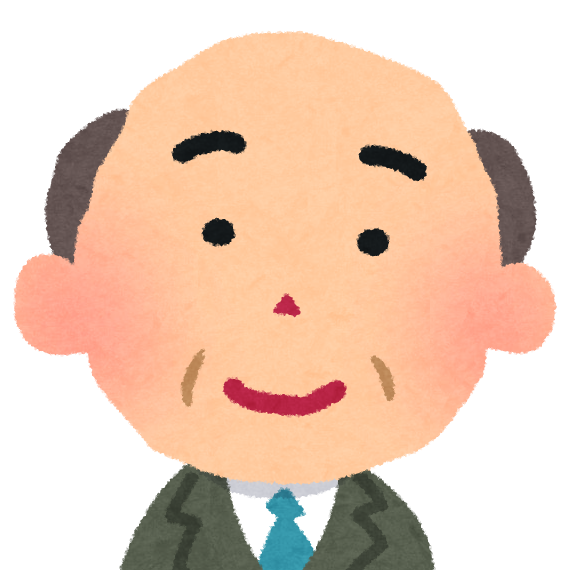 上司
上司いい飲みっぷりだね~
最近の若い人はお酒が飲めないから、心リセット君みたいな人を見てると気持ちがいいよ
 心リセット
心リセットすみません…気分が悪いので…トイレに行ってき……#$☆!@※#?!
お酒の場ならではの「暗黙のルール」がつらい
お酒の席って、独特のマナーがありますよね。
「上座・下座の位置」「乾杯の流れ」など…。
成人をしてお酒を飲めるようになったばかりなのに「これだから若いやつは気が利かない」と上司にいきなり怒られたりして、当時の私はそれが理不尽に感じていました。
中でも「上司のグラスに注ぐ」というルールはとても難しいですよね。
特におちょこだと量が確認しずらいし、気づくのが遅れるとイライラしながら上司が独りで注ぎ始めるし…
そんな“見えないルール”があるから、心の中で常に緊張状態になってしまいます。
本当はただの雑談の場なのに、どこか“評価される場”のように感じる。
その結果、「楽しむ」よりも「気を張る時間」になってしまうんですよね。
飲み会で気疲れしないための考え方と行動

完璧に振舞おうとしない
飲み会での立ち回りを100点にしようとすると、
「話を振られたらどうしよう」「場を盛り上げなきゃ」と頭がフル回転になります。
でも実際のところ、周りはそこまで他人の言動を覚えていません。
ですので、会話をするのが厳しいと思ったときは「聞く側」に回って気楽に過ごすのがおすすめです。
- 上司の話に対して軽く相槌を打ちながら、質問を挟む
「なるほど、そのプロジェクトは大変そうですね。特にどの部分が苦労しましたか?」といった、抽象的な質問であるほど相手の話す時間が増えて間が持つ - 共感で安心感を出す
強く同意する必要はなく、「そうですよね」「大変でしたね」程度で十分(激しく同意をしてしまうと、相手もさらに話したくなってその場を離れられなくなる恐れがあるため) - フェードアウトの言い訳を用意
「明日早いので」や「少し席を外してきます」といって、なにか聞かれたらさらにテキトーに答えて席を移動。ポイントは相手の話が一段落をした隙を狙うこと
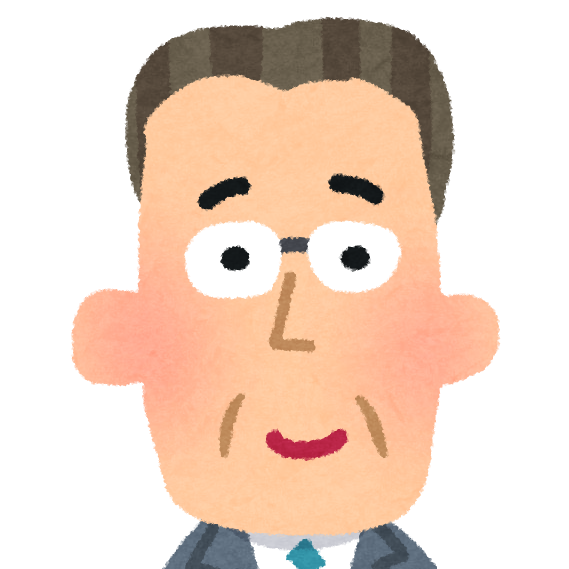 上司
上司私の若い頃なんかは、朝まで会社でプレゼンの資料を作って、その足で取引先に伺うのが当たり前だったんだよ
 若手社員
若手社員それはとても大変な時代でしたね!
眠くなった時はどうしてたんですか?
(深く質問したら、そのうち説教に変わりそうだからこのあたりで席を移動するかな)
飲み会の暗黙のルール対策
上座と下座の見分け方
上座は、出入り口から一番遠く、壁やソファがある位置を指します。
下座は、出入り口に近い場所で、運ばれてきた料理や飲み物の受け渡しが発生しやすい位置となります。
しかしこれは、お店の間取り等で参考にならない事があります。
悩みたくない場合は、事前に同期と合流してから入店をしたり、「どこに座るのがいいですか?」と聞いてしまうのがベストです。
乾杯の流れ
基本的には、乾杯の挨拶があるまでグラスに口はつけないです。
挨拶の直後みんなでグラスをあてると思いますが、席が離れている人のところまで行く必要はありません。正面と両隣の方+届く範囲の距離であてあって、誰かが飲み始めたら追従する形で飲めば違和感なくスタートができます。
お酒を注ぐタイミング
瓶ビールの場合は、グラスが3分の1程度になったら「お注ぎしてもいいですか?」と声をかけましょう。いきなり瓶を持って注ごうとするのはNGです。
熱燗の場合は、おちょこの中を覗くのではなく、「そろそろ少なくなっていませんか?」と適宜聞いてしまうのが無難です。
以上、飲み会の代表的な暗黙のルールと対策について紹介させていただきました。
でもルールは他にも探せばいくらでもあるためキリがありません。
一番大切なことは、ルールを気にしすぎて気疲れしない事です。
多少の失敗をしても「すみません、こういう場が慣れてなくて」と言えば大抵許してくれると思います。
自分が穏やかに過ごすことがまず大前提で、次に周りに多少の気を使うくらいが、飲み会で気疲れしない一番の考え方です。
まとめ

飲み会のあと、ひとり帰り道で「良い振る舞いができなかった…」「うまく話せなかったな…」って落ち込む夜、ありますよね。
でも、それはあなたが人の気持ちに敏感で、周りを思いやれる人だからこそ。
たとえ失敗しても、社会人として全然ダメなんかじゃありませんし、年齢を重ねるとその度に飲み会に求めるものも変わってきます。
無理に盛り上げたり、誰かに合わせたりしなくて大丈夫。
ちょっとした笑顔や、静かに話を聞く姿勢でも、しっかりと参加できています。
これからは、“参加する=頑張る”じゃなくて、“参加する=軽く関わる”くらいの気持ちでいきましょう。
それが、飲み会とうまく付き合ういちばんのコツだと思います。
もうすぐ忘年会シーズンですが、この記事が少しでもあなたの力になれたら幸いです。

コメント